スタビライザーとは
クルマが旋回するときに発生する車体の傾き(ロール)を適正に抑えるのがスタビライザーの役割です。
つまりは車の平衡を保つための部品です。
高速走行時のふらつきを改善し、レーンチェンジ時の安定性を向上させるなどの効果があります。
スタビライザーは別名【アンチロールバー】とも呼ばれています。
なので、ロールを抑えるのがメインの部品です。
メインと書いたのは、もう一つ車体の揺れを抑えるという効果もあるからです。
スタビライザーの作動仕組み
スタビライザーは棒が捻れる事による反発を利用した部品です。
この捻れるによる反発力を使いロールを抑えています。
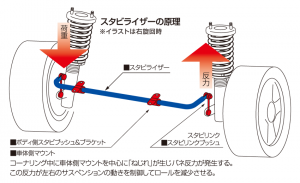
車がコーナーでロールしてる時に、内側のスプリングを縮ませる部品です!
最初に書いたように車を平行にするための部品なので、どちらかのスプリングが縮んだ場合、その逆のスプリングを縮ませることにより
平行を保たせる機能をしています。
スポンサーリンク
動作メカニズム
①直進時、②片側段差通過時、③コーナリング時に分けて、説明したいと思います。
①直進時
下の図は、3台の車が平坦な道をまっすぐ走っている状態を表しています。

一番左が普通の4輪独立懸架のクルマ、中央が左の4輪独立懸架のクルマにスタビライザーを装着したクルマ、一番右が車軸懸架のクルマです。
まっすぐ走っているときは、左右のサスペンションの長さは同じですので、スタビライザーは何の働きもしません。
当然ながら、車体も水平です。
②片側段差
次に、片側の車輪が段差に乗り上げたらどうなるでしょう。

当然、段差側のバネは圧縮されます。
このとき、もしスタビラーザーが無ければ反対側のバネは通常状態を維持しますので、車体も比較的水平を保てます。
ところが、スタビライザーが付いていると、これによって反対側のスプリングも無理やり縮められますので、スタビライザーが付いていないときよりも、車体は傾く事になるのです。
また一番右の車軸懸架のクルマは、左右のタイヤが1本の軸で繋がっているため、サスペンションがあってもどうしても車両は傾きます。
という訳で、スタビライザーを付けたクルマが片側段差を乗り越えると、独立懸架と車軸懸架の中間の挙動を示します。
ただしスタビライザーを太くし過ぎると、4輪独立懸架の効果が無くなり、
車軸懸架と同じ挙動になってしまいます。
またスタビライザーには、もう一つ別の弊害があります。
図にはありませんが、轍(わだち)を斜めに横切った場合、左右のタイヤが交互に段差を乗り越えます。
その場合、スタビライザーの揺り返しの反動と路面のうねりが重なって、車体が大きく左右に振られる事になります。
結果的に、更なる乗り心地の悪化を招きます。
スポンサーリンク
③コーナリング
逆にコーナーではどうなるのでしょう。
コーナーでは、車体上部が遠心力で外側に傾いて、内側のバネが伸びたら反対側のバネも伸ばそうとします。
このため、下の図の様に4輪独立懸架は車体が大きく傾くのに対して、スタビライザー付きは車体の傾きを抑える事ができるのです。

スタビライザーを付けると乗り心地は悪くなるものの、車体のロールを抑えるというのは、まさにこの理由なのです。
まとめ
スタビライザーって言葉だけでは分からない働きがありますね。
乗り心地にも影響する部品ですし、つけた方がいい部品でもありますが、
やみくもにいいモノをつけるのではなく、サスペンションとの相性が決め手になってきますので、
カスタムしたい方は専門ショップに相談した方がいいですね。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
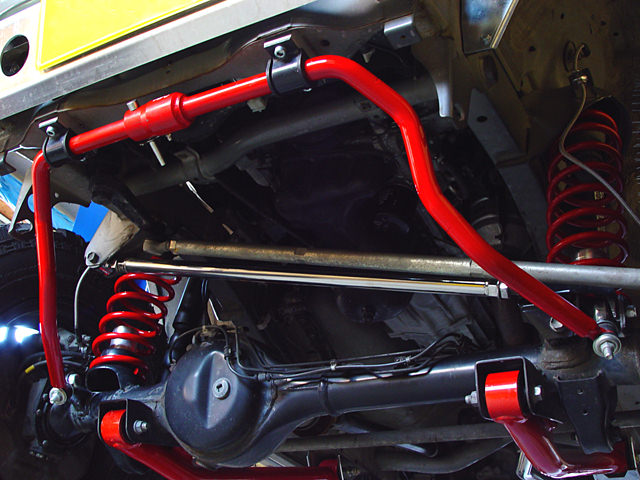


コメント